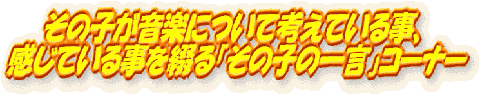
ひょんな事から「その子の一言」なるコーナーが出来る事になりました♪
私が音楽について考えている事、感じている事など軽いタッチで触れていきたいと思います。
| 1 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【ショパンの歌曲について】です。 ショパン・フレデリク・フランチシェク(1810 / 3 / 1~1849 / 10 / 17)は、その生涯で19曲のピアノ付き歌曲を残しています。知っていましたか?私は今回のプレポーランド公演で独唱させていただくことになり、深く調べる様になるまで、歌曲の存在をしりませんでした。(ショパンというと華麗なピアノ曲ばかりかと…)ところで、これらの歌曲はショパンの生前には出版されず、死後(1859年)友人のフォンタナによって収集、出版されました。ショパンは生前、出版の意志を持っていなかったらしいのですが、その為か、ショパンの歌曲は非常に簡素で、音楽の中心はあくまで歌のメロディーラインで、伴奏を受け持つピアノパートもショパンのピアノ作品とは比較にならないほど単純です。しかし、それだけに1曲1曲は、素朴な味わいがあり、決して作為的でないばかりか、ショパン個人の愛の想い出や故国を思う心が素直に感じられて心に迫ります。また、故国といえば、ショパンは生涯の半分近くをフランスで過ごしたのにもかかわらず、残された歌曲は全19曲、すべてがポーランド語。父の祖国フランスにいながら、生涯ポーランド人であり続け、祖国への愛国心を持ち続けたショパン。ショパン歌曲はそんな愛国心がちりばめられた歌曲です。CDも出ていますので気になった方はその子までお問い合わせください。 |
| 2 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【コンサート】について。 こんにちのように、聴衆がチケットを購入して、音楽会場に行って演奏を聴くという習慣が定着したのは、 いったいいつからなのでしょうか? どうやらそれは、バッハ以降のようです。それ以前は音楽を聴くためには、教会に行くか、宮廷や上流階級の館に招かれるか、自分達で仲間を集めて演奏するしかなかったようです。さてさて、どちらの時代に生きるのが幸せなものか??? |
| 3 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【コンサート】について。 こんにちのように、聴衆がチケットを購入して、音楽会場に行って演奏を聴くという習慣が定着したのは、 いったいいつからなのでしょうか? どうやらそれは、バッハ以降のようです。それ以前は音楽を聴くためには、教会に行くか、宮廷や上流階級の館に招かれるか、自分達で仲間を集めて演奏するしかなかったようです。さてさて、どちらの時代に生きるのが幸せなものか??? |
| 4 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【即興演奏】について。 こんにち即興演奏というと、ジャズを想像される事が多いかと思いますが、バッハを含め、バッハ以前の音楽界においては、即興演奏がごく一般化されていました。例えばバッハの「ブランデンブルク協奏曲第三番ト長調・二楽章」は、二つの和音が記されているだけにすぎません(まさしくジャズのリードシート状態!)これは、バッハ自身が独奏した部分にあたり、どうせ自分が演奏するのだからと、わざわざ書き記す労を取らなかったのです。もし1回目の演奏でいまいちだったら、次は別のやりかたで演奏すればいいや!と、こんな自由があるところが即興演奏の面白さでしょう。私もジャズが大好きで、自分自身もジャズバンドでピアノを弾いていますが、そんな赤羽家の毎朝の食卓はTVをつけることがなく、1枚のCDが延々とかかっています。そのCDの名前は「ケルンコンサート」私の大好きなジャズピアニスト「キースジャレット」がすべて即興でピアノ演奏したケルンでのコンサートライブ版です。こんなふうにピアノが弾けたらなぁ!と毎朝考えさせらてしまう、素晴らしいプレイの連続です。 |
| 5 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【ピュタゴラス】について。 ピュタゴラスと音楽に、いったいどんな関係があるの?その子がピュタゴラスについて語る日が来たとは、世も末かって…って思っている人、多い事でしょう!おおげさな。実は音の高さが弦の長さや重さに反比例するんだという法則に初めて気付いたのが他ならぬ偉大な古代ギリシャの哲学者ピュラゴラスだったんです。ある日、道を歩いてたピュタゴラスが鍛冶屋の前を通って気付いたそうです。私なんていつもぼけっと散歩をしているのに、やはりインテリは着眼点が違うのね。 |
| 6 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【ドイツ読み】について 洋子先生や、指揮者の先生が音の名前をドイツ語で言うことがあります。一度覚えれば簡単なので、この機会に覚えてみましょう!ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ・は(日本読み)ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドは(イタリア読み)Cツェー・Dデー・Eエー・Fエフ・Gゲー・Aアー・Hハー これが(ドイツ読み)です。日本では小中学校ではイタリア読み、日本の音楽大学、音楽界ではドイツ語読みが一般的なようです。 |
| 7 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【楽譜】について こんにちのように、楽譜に横線を引く事を始めに思いついたのはイタリア人のグイド・ダレッツォ(990頃~1033頃)であるといわれている。だからそれ以前、11世紀以前の楽譜には線がなくったから音符(当時はネウマ)の高低の差が明確ではなかった。1本横棒があれば、てきめん!わかりやすくなる。考えてみれば簡単だけれど、コロンブスの卵。あっぱれダレッツォ!という感じですね。 |
| 8 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【ドの起源】 17世紀以前は、「ド・レ・ミ」じゃなくて「ウト・レ・ミ」と歌っていたらしい。でも、ベルカントではuという口の小さい発声が歌いにくいということで、改良しよう!ということになって、大きく口を開ける「ド」になった。なぜ「ド」なのかは、はっきりわかっていないが、聖歌隊にとって一番歌う事の多い言葉の1つである「ドミヌス(主なる神)」の「ド」であることは、まず間違いないと思われている。ところで以前、この話が赤羽家で話題になった時の親子の会話。―その子「お母様、ドレミの『ド』の起源て何だと思う?」―洋子「うーん……(しばし考えて)…ドーナツの『ド』じゃない!?」 |
| 9 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【黒鍵】について。 以前、音のドイツ語読みを覚えたけど、(Cツェー・Dデー・Eエー・Fエフ・Gゲー・Aアー・Hハー ) これはピアノでいう「白鍵」だけ。じゃあ「黒鍵」はどう、読むのか。これは意外と単純作業で、♯(シャープ)・♭(フラット)は、それぞれ単語を足せばOK。どんなふうにかというと、日本読み(ハニホヘトイロ)には♯の時は「嬰(えい)」を♭の時は「変(へん)」を頭に、ドイツ読みでは♯の時は「is(イス)」を♭の時は「es(エス)」をお尻に、足してください。例外がひとつだけあってHハーの♭はHesじゃなくてBです。ちょっとややこしかったかな?わからなかったひと、もう少し詳しく知りたい方は個人的にその子まで!優しくお教えいたします。 |
| 10 | ―――その子が音楽について考えている事、感じている事を綴る「そのこの一言」コーナー――― 今日は【テノル】について。 「テノール」の語源は、「テノル」から来ています。「テノル」とは、旋律の動きにおける、「中心となる音」を指します。ルネサンス時代聖歌隊は男性のみで、のちから女性が加わった事がここからもわかりますね。 それにしても群馬の代名詞というと「かかあでんか と 空っ風」なのでしょうか?私が東京に出ていた時「群馬出身です」というと、必ず「群馬の女性ってかかあ殿下なんでしょ!?」と聞かれたのを覚えています。そして「その子の家では、やっぱり お母さんの方が強いの?」と聞かれたものでした。「うーん…」群馬県人が皆そうなのか、我が家だけなのか答えにつまる私でした。ルネサンス時代には考えも及ばなかった事でしょう。 |
合唱団のトップページ / 高崎第九のあゆみ / ベートーヴェンと第九 / 海外公演
