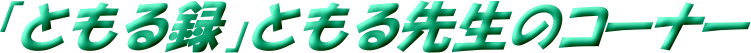指導者・バス 住谷 伴(ともる)先生のコーナーです
ともる録1 2004.7.29たいむず588号
ヨーロッパの6.7月は晴天が多く、一年中で最も快適な季節です。
高緯地域に加え、サマータイムを実施しているので、日の入りは午後10時近くになります。
夕食後街へ出てウィンドーショッピングをしたり、公園や野に出て散歩をするのが楽しみです。
公園のベンチで夕暮れ時のまどろみからふと我に帰ると、11時をすぎてしまうこともしばしば。
R.シュトラウス作曲「たそがれの夢」「あした」などは、この黄金の時を歌っています。
第九でドイツ語に興味を持たれた皆さん、ドイツ歌曲にも触手を伸ばしてみてはいかがですか。
ともる録2(ビール1) 2004.8.5たいむず589号
皆さんは今年の猛暑をいかがお過ごしでしですか?
ひと汗かいた後のビールはおいしいですね。
ビールと聞いてドイツビールを思い浮かべる人は間違いなくビールマニアです。
ドイツには"ビール純粋法"という法律があり、国家がドイツのビールを守っています。
水・麦汁・酵母・ホップのみを原料とした品物に"Bier"の名が与えられます。
製法・地域により、実に多くの種類・銘柄があります。
私がもっとも感動したのは、バンベルグ特産のRauchbierです。
直訳すると「くん製ビール」。くん製にした大麦を用いたスモーキーなビールです。
独特なコク深い味わいがあり、おつまみが必要ないと思います。
近年・県内の酒店でも見かけるようになりました。
珍しいもの好きの人に、是非おすすめします。
ともる録3(ビール2) 2004.8.19たいむず591号
前回に続き、ビールについてお話します。
ドイツで味わえる物として、ご存知プルゼニ発祥のPilzener,軽い口当たりでさわやかなKolsch,茶色でコクのあるAlt,ろ過していない(白く濁っている)Weizen,炭酸が多いWeissbierなどが代表格です。
言うまでもなく出来たての樽出しが一番です。
ドイツ各地をめぐると、必ずその土地の地ビールを楽しむことができます。
「これだけ飲んでいるのに、ともるの腹はなぜ出ていないのか?」と思われるかも知れません。
実は,私はアルコールに弱いので,低アルコールビール(Alkoholfreies Bier)を愛飲しています。
上記のほとんどに低アルコールビールが造られています。
また、子供用として、アルコールを含まない、黒くて甘いMalzbierが売られています。
尚、ドイツではビールは酒類(Spirituose)ではなく食品(Lebensmittel)です。
朝、工事現場で働く人々がビールをラッパ飲みしている光景を目にしましたが、発酵飲料で栄養補給をしていたのでしょう…。
ともる録4(秋) 2004.9.9たいむず594号
9月に入り、時折残暑に見舞われるものの、確実に秋の気配が感じられるようになりました。
中部・北部ヨーロッパでは、8月に今の日本と同じ季節を迎えます。
8月に入ると曇りや雨の祖が多くなり、長袖の服が必要になります。
ただし昼間の時間はまだ長いので、曇りの日などは時計が「8時」を示していると、午前だか午後だかわからなくなることがあります。
8月のある日曜日、体調不良で寝込んでいた日本人の友人が私に電話を掛けてきました。
「今9時だけれど、朝?それとも夜?」という質問でした。日曜日の9時では、朝でも夜でも商店はほとんど閉まっているので、窓から外を眺めただけではわからなかったのでしょう。
私は一日遊んでいたので、「夜だよ。」と答えられましたが…。
テレビ・ラジオ等を持たずに外国で生活をすると、こんな不思議な体験をすることがあります。
ともる録5(ビール3) 2004.10.7たいむず598号
今回はドイツ周辺の国のビールについてお話します。
ベルギーはドイツをしのぐほどのビール消費国です。
修道院で醸造されるビールがあり、その品質の高さには定評があります。
また、酵母菌を添加せず、空気中の菌で発酵させるビールも有名です。
さらに、製造過程で果物を加えて発行・熟成させる物もあります。
さくらんぼのビール、Kriekはベルギーを代表するフルーツビールでしょう。
他にブルーベリー、木いちご、桃を加えたビールもあり、女性に人気があります。
残念ながらフルーツビールには低アルコールは存在しません。一方、オランダでは、ラガータイプが好まれているようです。
特にHeinekenは国民的な人気を誇っています。
緑色の缶入りで、見た目にもおしゃれです。
私はかつて、市の大規模な祭りの翌日にアムステルダムを訪れたことがありますが、街中に緑の空き缶があふれていて、閉口した思い出があります。
ともる録6(Streik!) 2004.10.14たいむず599号
日本のプロ野球で初めてのストライキが決行されたのは記憶に新しいところです。
ドイツでは1990年代前半、国有鉄道の民営化に際し、労使の意見が激しく対立し、Dusseldorf近郊でストライキ(Streik)が決行されました。
中距離列車、市電、バス、更に駅周辺の清掃がストップし、街は大混乱に陥りました。
駅の時刻表は"Streik"で埋めつくされ、駅前は放置されたゴミが乱舞しました。
幹線道路、アウトバーン更に自転車道も大渋滞。
地域経済全体が大打撃を受けました。
この時の光景はまさに世紀末と呼ぶにふさわしいものでした。
結局労使双方が歩み寄り、民営化されましたが、当時20代の若造であった私は、ドイツ人の根気強さ(しぶとさ?)に感心してしまいました。
ともる録7(旬の味覚1) 2005.1.13たいむず609号
私は子供の頃から好奇心(ヤジ馬根性?)が強い男で、いろいろな食べ物に挑戦してきました。
ドイツ滞在中もさまざまな物を口に入れてみました。
これからお話する内容は単なる笑い話として、真剣にお考えにならないようお願いします。
すべての花がいっせいに花を咲かせる5月、森の木陰ではワラビ、ゼンマイ、コゴミ、などが芽を出します。
私は森の奥深くまで入り込み、山菜採りに夢中になりました。
日本ではアク抜きが必要ですが、ドイツの山菜は低湿度のためか、ゆでるだけで食べられます。
ただし味そのものが薄く、ダシ入り醤油で煮ないと話しになりません。
尚ヨーロッパ人には山菜を食べる習慣がないので、全く放置されています。(もったいないねェ!)
ともる録8(旬の味覚2) 2005.1.27たいむず612号
ドイツの春は花の便りで始まり、野原では青々とした若葉がまぶしい季節です。
ヨーロッパの野草は日本ほど多種ではありませんが、食べられるものも少なからず存在します。
まずは西洋タンポポ。
尖った葉をそのままサラダにします。ドレッシングはオリーブオイル、バルサミコ、岩塩、ブラックペッパーで作れば最高です。
苦味が強い味ですが、ゆっくり噛んでいると体が温かくなり、活力が湧いて来ます。
畑の端にはヨモギが茂り、干してヨモギ茶で楽しむことができます。
ツクシは佃煮に、スギナはおひたしやお茶で楽しめます。
尚、スギナはドイツの薬局で立派な煎じ茶として、結構な値段で売られています。
ともる録9(旬の味覚3) 2005.2.24たいむず617号
ヨーロッパの中部では、夏になると多種の果実が人々を楽しませてくれます。
針葉樹の陰では、ブルーベリーが小粒で紫色のかわいらしい実をのぞかせます。味は薄いのですが、口に含むとほんのりとした香りでさわやかな気分を楽しむことができます。
山辺雑木林では、黒イチゴ(Brombeere)がルビーのような房をつけて実っています。アリなどの昆虫が浸入していて食べる際に神経をつかいますが、ほどよい酸味と甘味が食欲をそそります。
6月下旬、友人とブレーメン郊外散歩していたところ、驚いたことに街路樹にプルーン(Pfiaume)が植えられた区間がありました。ちょうど食べ頃だったので、周囲を気にせず頬張ってしまいました。
ともる録10(旬の味覚4) 2005.9.1たいむず649号
8月下旬頃から雨天の日が多くなり、秋の涼しさが感じられるようになりました。
秋の味覚のひとつにキノコが数えられる と思いますが、ドイツでも秋になると日本と同様に多くのキノコが生えます。
森の中ではスギヒラタケ、ナラタケ、ホコリタケ等を見かけました。私はキノコ図鑑を携えてキノコ狩りを楽しみにしていました。おいしそうなキノコに出会っても、図鑑の写真と同じ種の物なのかどうか判別できず諦めることもしばしば…。
ある日曜日、森を散歩していた時、直径12センチほどのカサを持った紫色のキノコが目にとまりました。食べられる(Essbar)のか毒(Giftig)なのか分からないまま家に持ち帰りました。ゴミ等を取り除いて迷ったあげく、オリーブ油で炒めて食べることにしました。
「明日目が?めるように!」と祈るような気持ちで口に運んだ瞬間、「うまい!」と叫んでしまいました。結局丸ごと食べてしまい、その夜は体が温まり心地よい眠りに就きました。勿論翌日も元気でしたが…。
後日詳しく調べたところ、立派な食用キノコ(Speisepilz)でしたが、随分無茶をしたものだと、今になって苦笑しています。
ともる録11(旬の味覚5) 2005.9.15たいむず652号
ヨーロッパでは9月中旬を過ぎると急に秋が深まります。ただし、スーパー等に並ぶ食材は日本ほど季節感がありません。
しかし、魚介類は格別で、秋から翌年の早春にかけて旬を迎えます。
北海の幸の代表格はムール貝です。主にベルギー、オランダで好んで食べられています。
調理法はいたって単純。大きな蓋つきの専用鍋に、生の殻つきムール貝をどっさりと入れ、白ワイン、ニンニク、香草、塩・コショウを加えて蒸すだけ。これで濃いダシの出る一品料理の出来上がり。
ビールとフライドポテトとともにいただきます。味噌を加えると更においしくなるでしょう・・・。
私はベルギーで何度か味わいました。
白ワインのアルコールが残っていて、半分も食べないうちに酔ってしまい、朝までぐっすりと眠ってしまいました。
合唱団のトップページ / 高崎第九のあゆみ / ベートーヴェンと第九 / 海外公演