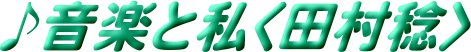指導者・テノール 田村 稔
2006年・2007年の「たいむず」に連載された「音楽と私」は、指導者 田村稔先生の音楽に関する体験や、考えていることをいろいろ書き綴っていただきました。
 2007.8.16
2007.8.16
合唱団のトップページ / 高崎第九のあゆみ / ベートーヴェンと第九 / 海外公演
音楽と私(第1回)
第1回はやはり第九についてのお話をしたいと思います。
私と第九との初めての出会いは、音楽大学に通う2年のときでした。東京には、プロの合唱団がいくつかあり、そういった合唱団も男性が不足していて、音楽大学の声楽専攻の男性にもよくコンサートや、芸能人のバックコーラスなどのエキストラの仕事がまわってきます。中でも年末になると多いのが、第九の合唱のエキストラです。私もいろいろ合唱のアルバイトをしましたが、第九の場合は本番に譜面を持てないので、暗譜で歌えるのが条件になり、いつも断っていました。
ある時、合唱の仕事の元締め的なことをしていた友人から誘いを受けました。その時も初めは断ったのですが、なんとかメンバーを集めたいその友人から「周りにあわせて適当に歌っとけばいいよ!」と言われ、当日まで1週間あるから練習すればなんとか覚えられるだろうと思い引き受けてしまいました。いざ楽譜を手に入れ曲を聴いてびっくり!特に中間部分の2重フーガのあたりは複雑でどうにも自分一人の練習では覚えられそうにありませんでした。それから1週間ウォークマンで聴きながら常に楽譜を手にできる限り、第九と格闘しました。
不安の中、本番の日がやってきました。演奏会はあっという間に終わりました。周りから聴こえてくる圧倒的な声の力につられ、必死に歌う中、日常生活では決してありえない、なにか異次元の空間に入りこんだような貴重な体験をしました。自分がちゃんと歌えていたかは自分でもわかりませんでした。(笑)
音楽と私(第2回)
音楽大学の学生の頃、プロ合唱団を通じて学生に回される合唱のエキストラの仕事をいろいろしたことを前回書きましたが、中島みゆきのバックコーラスをしたときのことを思い出しました。
歌志望の学生にまで回される仕事は切羽詰まった仕事も多く、そのときも確か本番数日前に回ってきた話だったと思います。集まるだけの男性メンバーを集めて、曲名は忘れてしまいましたが、曲のさびの部分を、全員で中島みゆきと同じメロディーを歌うという簡単な仕事でした。楽譜とデモテープが送られてきたと記憶しています。
学校の練習室に集まり、はじめは楽譜を見ながら譜面の通りのリズムで歌っていましたが、デモテープを聴くと中島みゆきは微妙にリズムを自分流に変えて歌っていました。話し合った結果デモテープの中島みゆきの歌い方で全員が歌うことになりました。何度もテープを聴いて苦労してその歌い方を練習しました。本番を終えてその後わかったのですが、合唱は当然譜面の通りのリズムで歌えばよかったのです。合唱団員全員が中島みゆき流の節回しでそろって歌っては、本人もさぞ歌いにくかったと思います。
音楽と私(第3回)
卒然話は前回のものと飛んでしまいますが、留学時代の話になります。僕が音楽を勉強したザルツブルクと言う町は、カトリック教会のオーストリア圏の総本山的な町で、モーツアルトが生まれた町として知られています。モーツアルトの当時はローマカトリックの直轄地で、大司教が治めた町でした。
今でも大きな教会がいくつかあり、僕は、その中のフランチスカーナ教会のソリストに登録していました。ソロを歌わないときは合唱を手伝うのですが、毎週日曜日に室内オーケストラ付きのミサ曲を歌うため、譜読みがとても大変でした。木曜日の夕方の練習と当日の朝の練習だけで、毎週新しいミサ曲(5曲くらいの合唱曲でカトリックのミサのときに歌われ、歌詞はラテン語の歌詞で全ての曲が同じ歌詞で作られている)を歌います。合唱の方々はみな地元のアマチュアの人です。どうして1~2回の練習で歌えてしまうのか不思議でしょう?
教会の合唱の皆さんは何年も(何十年も)歌っているから同じ曲を過去に歌った経験があり、なんとなく歌えてしまうということもありますが、実は、教会の響きがあまりによく、かなりあやしい合唱でもそれらしく聴こえてしまうのです。時には1パートが全部落っこちてしまっても聴いていてそれほど違和感がないというのが実際のところでした。教会の伝統恐るべし。
音楽と私(第4回)
ザルツブルクに留学した私は、1年分の留学資金しか用意していませんでしたので、長く留学するためには仕事を始めなければなりませんでした。そこでザルツブルクのオペラ劇場の合唱団の仕事を得ました。ある年は1シーズンほぼ全ての演目に合唱で参加し、得難い経験をしました。
オペラ劇場には、床屋があり衣装屋があり美容師がいて、小さな町のようです。もちろんスタッフ用の食堂もあり、幕間に食事をしたり、ビールを飲んでいる歌手もいます。専属の合唱団員の給料は低いのですが、家族を持って生活している人も多く、なんとか生活するくらいの給料はもらえます。
仕事内容は午前と午後、1時間半の練習を一日に2回するだけです。公演がある日は午前の練習と本番の舞台となります。演目は年間10種類程のオペラで、イタリアのオペラもほとんどドイツ語で上演されました。オペラ座の合唱団のメンバーはみな本当に個性的な人が多く、歌はともかく芸達者でした。海外のオペラを見ると合唱の人達が舞台にとけ込んですごく自然に振る舞っているのをご覧になったことがあると思います。
歌はともかくと書きましたが、本当に歌はともかくなのです。譜面を読めない団員も多く(もっとも譜面の読めないソリストもいるくらいですから)、僕のとなりでいつも歌っていたテノールのおじいさんは時々ソプラノと同じメロディを歌っていました。それに安心して、僕もうろ覚えで舞台に出てしまったこともありました。もちろんウイーン国立歌劇場の合唱のメンバーではあり得ないかもしれませんが、少しローカルなザルツブルクの劇場では、お客さんも寛大なのです。
音楽と私(第5回)
夏は世界各地で音楽祭が開かれますが、ザルツブルクも音楽祭の町として、この時期大変にぎわいます。多くの有名音楽家が集まり、市内10数カ所の会場で毎日演奏会が開かれ、それを目当てに世界中から音楽愛好家が訪れます。この時期、町のカフェや通りで有名演奏家に出会うこともよくあります。小さな町は一時、アメ横のようなにぎわいとなります。町の中心のゲトライデ通りは、昼間、歩行者天国になっていますが、思うように前に進めないくらい人がたまってしまいます。
そんな夏の音楽祭の演奏会と日本で開かれる演奏会と何が違うかというと、お客さんの服装が違います。皆正装をして演奏会を聴きに行きます。男性はタキシード、女性はドレスです。男性はダークスーツでも大丈夫ですが、何となく居心地が悪い感じです。僕もザルツブルクに行ってすぐに、先輩から必要だからといわれタキシードを新調しました(第九の合唱を歌うときに今でも着ています)。ザルツブルクでは舞踏会や演奏会に若いうちから正装をする習慣があり、そういった衣装も日本よりは安かったように思います。いざタキシードを着てお目当ての演奏会に出かけ、休憩のときにシャンペンでも飲もうものなら、日常から離れセレブな気分が味わえます。
ザルツブルク音楽祭のチケットは、半年程前に申し込むと抽選がおこなわれて、当選した人のみ買うことができます。これがなかなか当たりません。チケットがとれなかった音楽ファンが、本番前に会場周辺にたくさん集まって来ます。昔はダフ屋が出て実際の価格よりかなり高額で売られていたそうですが、最近ではそういった行為はかなり厳しく禁じられています。
そんな中で僕は、かなり良い確率で本番直前に格安で、または時には無料でチケットを手に入れました。チケットが欲しい人は、Suche(探す、求む)と書いたカードを手に持ってホールの前をうろつくのですが、たくさんのそういう人の中で、なぜか僕の所に余ったチケットを譲ってくれる人が来ます。危険がなさそうに見えるのか、わざわざ東洋から来た青年に(当時の僕はヨーロッパ人からみると少年に見えたかもしれません)同情するのか、理由はよくわかりませんでしたが、とにかくチケットを譲ってもらうことができました。
出かけるとだいたい演奏会場に入ることが出来た中で、どうしても聴くことができなかったのが、パヴァロッティの独唱会でした。ピアノ伴奏で生の声をじっくり聴く機会だったのですが、そのコンサートの後パヴァロッティはマイクを使う演奏会を開くことが多くなってしまい、大変残念でした。ただ主催者が、ホールに入れなかった人のために近くの教会広場でパブリックビューイングを開いてくれて、大画面の中、巨大な顔で歌うパヴァロッティを楽しむことができたのも良い思い出です。
音楽と私(第6回)
留学時代の話が多くなってしまいますが、留学当初は、住む家も確定せず、学校も決まらず、トランクを引きずっての放浪者のような時期があり、今考えてもつらい時期でした。
日本でレッスンを受けたドイツ人の先生を頼って3週間くらいフライブルクに滞在したときのことです。夏のヨーロッパは日が長く、夜の9時を回ってもまだ外が暗くなりません。それなのにお店は6時頃にしまってしまい、旅行者がいられるのはレストランとかバーのような所に限られてしまいます。お金の少ない留学生にとって毎日レストランへ行くこともできず、昼間は音大の練習室で練習し学生食堂でお昼を食べ、夕方スーパーで買ったパンやハムなどをガストハウス(安く泊まれる宿)でわびしく食べる日が続きました。
ある日の夕方突然の大雨で身動きができなくなってしまったのが、劇場の前でした。催し物をチェックすると、オペラ「トスカ」と書いてありました。これはチャンスとチケット売り場へ急ぎましたが、ほとんど開演時間になっていて人影はありませんでした。あきらめかけていた僕の所に女性が近づいてきて「チケットを探しているのですか?」と聴いてきたので「はい」と答えたら1枚余っているチケットを譲ってくれました。
開演時間になっていたので、そのチケットを持って会場に急ぎました、案内係にチケットを見せ、入り口のドアを案内され、一歩会場に入った僕はあっけにとられて、何が起こったのか一瞬理解できませんでした。イメージの中ではドアを開けると広い会場にオーケストラピット、華やかな雰囲気を期待していたのに、そこはこじんまりした小さな会場で舞台も小さくオーケストラもありません。何と同じ時間にはじまる演劇に来てしまったのです。今考えれば、チケットを一応チェックしてから買うべきでした。留学したての語学力の僕には演劇の内容がさっぱり解らず、1幕終了後に寂しく宿へ引き返しました。
音楽と私(第7回)
東京文化会館での演奏会です。海外の超一流の歌い手を集めて、ガラ・コンサートというのが開かれました。
ミレルラ・フレーニ、ニコライ・ギャウロフ、アグネス・バルツァなどが歌ったと思います。その中に当時はまだあまり有名でなかった、フランコ・ボニゾルリというテノールがいました。それまで聴いたことのなかったテノールで特に期待はしていなかったのですが、その通り、声はくぐもって音楽的にも何も考えていないようで、1曲目のオペラ「トゥーランドット」の中のアリア“誰も寝てはならぬ”も曲の途中でオーケストラと、ものすごくずれていってしまい、曲の最後の高音もそれ程よくありませんでした。
そのテノールがコンサートの後半にもう一度登場しました。今度の曲はオペラ「トロバトーレ」の“恐ろしき炎を”という最後に高いドの音(三点ハ音)が出る有名な曲でした。先ほどの演奏のように曲の途中までは、やはりあまり感心しない演奏だったのですが、曲の最後の最高音を聴いた瞬間に、全てが変わりました。
天井に立ち上がり降り注ぐような見事なテノールの高音に、酔いしれました。そのとき初めて声の本当の力を知りました。一瞬の声の中に全てのドラマがあるということが体験できました。客席の熱狂に満足してスキップをしながらボニゾルリはそでに帰ってゆきました。一声だけで観衆を熱狂させるような歌声はそのとき限り聴いていません。
音楽と私(第8回)
今回も記憶に残る演奏会のことを書いてみようと思います。
たくさん聴いた演奏会を思い浮かべて見ますと、ある演奏会全体ではなく、前回書きましたフランコ・ボニゾルリの歌った高音とか、ある演奏会の一部分が強く心に残っています。そんな中で記憶に残っているのが、アンドレ・ワッツのピアノリサイタルで聴いた、ピアニシモです。
東京文化会館の大ホールでしたが、力強い演奏の箇所よりも何より、ベートーヴェンソナタ「月光」の1楽章の途中で現れたPPの響きに心を奪われました(有名な「月光」のメロディは3楽章)。情熱的な中にみせたとびきりの繊細な表現に意表をつかれた感じでした。
「歓喜の歌」の中にも、とびきり美しいピアノの部分があります。おわかりでしょうか?そうです。Ihr sturzt nieder, Millionen ?の部分です。
音楽と私(第9回)
今回のテーマは、突然又飛躍してしまいますが、どんな演奏が人を感動させるのでしょうか。
うまい演奏とか、テクニックが優れている演奏ということが思い当たります。確かに秀でた技術を持ったプロの演奏は人を感動させる力を持っていますが、それだけではないような気がします。
かつてキーシンのピアノリサイタルを聴いたときに、難しい曲を事も無げに楽しそうに弾く姿に凄いとは思いましたが、感動は覚えませんでした。それに比べ、フジコ・ヘミングの演奏は技術的にはかなりあやしいのですが、思わず引き込まれる力があります。
この二人の違いは何か考えてみると、フジコ・ヘミングのほうは、波乱に満ちた生涯がテレビなどで紹介され、よく知った上でその演奏を聴いているという点です。演奏を聴きながら、その人の生涯がダブるのです。キーシンも人に言えない努力により今の技術を身につけたのだと思いますが、演奏からは聞こえてきません。ヘフリガーの歌はとても苦しそうで、音楽的な基本を外している部分もありますが、音楽にすべての人生をかける気迫が伝わって、感動させられます。やはり人を感動させられるのは、人の心ではないでしょうか。その演奏にどれだけ自分の人生をかけているかが問われるのだと思います。
皆さん!心を込めて「歓喜の歌」を歌いましょう。
音楽と私(第10回)
僕の好きな指揮者の一人に、カルロスクライバーがいます。
指揮者には何でもかんでも録音してしまう人もいれば、クライバーのように本当に自分らしい表現ができる曲だけを選んで最高レベルの演奏をする指揮者もいます。録音している曲は少ないけれど、そのどれもが録音史上燦然と輝く名演ばかりで、特にベートーヴェンの交響曲4番と7番が好きです(残念ながら第九は僕の知っている限りでは録音していません)。オペラではウェーバーの「魔弾の射手」、ベルディの「椿姫」「オテロ」などがあります。
僕が二十歳くらいのとき、スカラ座の引っ越し公演で、その「オテロ」を聴く機会がありました、学生だった僕には本当に高いチケットでしたが、電話でやっとのことで手に入れました。当時は海外オペラの引っ越し公演は少なく、短時間で完売でした。
テノールは脂の乗り切ったプラチド・ドミンゴです。始まると同時の激しい嵐の場面を、湯気が出んばかりに熱演するスカラ座のオーケストラとそれを指揮するクライバー、城壁の上で凱旋の歌を高らかに歌うドミンゴは、公演前から話題沸騰でした。夢にまでみたそのオペラ当日、なんとJR(当時は国鉄)が事故で止まってしまったのです!(涙) 伊勢崎まで車で行って、いつ着くかわからない各駅の東武線を使ってNHKホールに着いたのはもう2幕も終わり頃でした。ロビーに流れるモニターのスピーカーからは、白熱したオテロとヤーゴの2重唱が聞こえていました。
数日後FMですべての演奏を聴くことができました。やはり始めのシーンはすごかった。
音楽と私(第11回)
前回指揮者のことを書きましたので、今回もその流れで僕にとって印象深いもう一人の指揮者カラヤンを取り上げたいと思います。
カラヤンが音楽祭の直前に亡くなってしまったのは、ちょうど僕がザルツブルクで勉強しているときでした。カラヤンの住んでいた家はザルツブルク近郊のアニフという町にあり、郊外の道を車で通ると大きな家が遠くに見えました。
カラヤンは故郷のザルツブルクで、復活祭の音楽祭と夏の音楽祭をしきっていました。音楽祭の運営を助けるために、オペラの場合など、演出、舞台監督から、指揮までできるところはすべてカラヤン自身でやっていました。
カラヤンが亡くなる年の復活祭の音楽祭でプッチーニの「トスカ」を聴くことができました。テノール役のカヴァラドッシは前の年にリサイタルを聞き逃したパヴァロッティでした。カラヤンの指揮ぶりは皇帝という感じでとにかくかっこ良かったです。音楽祭のオーケストラピットはとても大きくそこにいっぱいの大きなオーケストラで、ベルリンフィルの管楽器がとにかく華やかでつややかに響き渡っていたのを記憶しています。その年の初夏、突然亡くなってしまいました。夏の音楽祭の代役は急遽ショルティが務めましたが、もうひとつ盛り上がりませんでした。アニフの町の小さな教会にカラヤンの墓があり多くのファンは旅の足を伸ばして墓参りをします。
音楽と私(第12回)
先日の日曜日(9/24)、宇都宮で合唱コンクールの関東大会が開かれました。
出場校は、各県の予選を勝ち抜いた優秀な高校ばかりですが、それにしてもレベルの高いコンクールでした。古今東西の難易度の高い合唱曲を見事なハーモニーで一糸乱れず歌う合唱を聴かせてもらいました。
それぞれの高校が、先輩の培ってきた伝統を守り、自らのプライドと名誉をかけて、10分にも満たない曲を何ヶ月も、数百時間の時間をかけて緻密に仕上げた合唱は、ある意味プロよりもレベルが高い所があります。
清水先生率いる富岡東高等学校も群馬県代表として参加して、透明感のある豊かな響きで、鈴木輝昭作曲の超難曲に堂々と取り組んでいました。真剣に取り組む人の音楽は感動的です。
音楽と私(第13回)
先日、やはり楽器の中で最高の(人の心を揺り動かす力があるという意味で)楽器は人の声だと実感させられる演奏会を聴きました。曲は、ヴェルディ作曲「レクイエム」です。
レクイエムとは本来カトリックの教会で、故人を偲んで催されるミサの曲ですが、多くの作曲家が有名な「レクイエム」を作曲して、現在では純粋に演奏会で取り上げられます。ヴェルディ作曲の「レクイエム」の編成は第九と同じオーケストラ、4人のソリスト、合唱で、宗教的な曲とは思えないドラマティックな音楽です。どちらかというとコンサート形式のオペラを聴いているような感じです。セットや演技がない分、すばらしい歌手たちの音楽に集中できてより音楽的な興奮を味わえたように思います。
生の声は力はやはりすばらしいのです。実際の生の声の音量より、CDで聴く音量はいくらでも増幅できますが、聞き手がその場所にいる空間に響き渡る、人間の声の力はCDでは再現できません。私たちも、お客さんの心に一生残るような歌声を目指してがんばりましょう。高崎第九の演奏会を生で一度聴きたいものです。
私と音楽(第14回)
皆さんご存知の通り、今年はモーツァルト生誕250周年記念の年にあたり、各地で記念の演奏会や催しが開かれています。モーツァルトは4才でピアノを始め、6才で作曲をし、14才では、すでにイタリアのミラノで初めて作曲したオペラを大成功させています。
そんな天才作曲家モーツァルトの音楽は、第九のように、聴く人を熱狂させるベートーヴェンとは対照的に人の心に安らぎを与えます。モーツァルト療法というのがあったり、その音楽を聴かせると牛がよくミルクを出したり、酒造りの現場でその音楽を流すと発酵がよく進むという話まであります。
クラシック音楽の中でも好感度が抜群なのがモーツァルトです。けれど、モーツァルトの音楽を、ただ耳ざわりが良い軽い音楽ととらえてしまうとその本当のすばらしさを見失います。実際演奏者がモーツァルトを演奏するときには、そこに一分の隙もない完璧さにたじろぎ、演奏の怖さを感じます。ほんの少しのミスも音楽を壊してしまう、厳しさがあります。子供でも弾く、単純なピアノソナタにも、熟練したピアニストでさえその本質まで到達できない奥深さがあるのです。
私と音楽(第15回)
今年、モーツァルト生誕250年にあたることはよく知られていますが、シューマン没後150年ということをご存知ですか。
1810年に生まれ1856年に亡くなって今年が150年目にあたります。シューマンはロマン派の作曲家の中で最も中心的な作曲家です。
初めピアニストを目指し、指の故障からその夢を断たれると、ピアノへの思いからたくさんのピアノ曲を作曲しました。また自分の師匠の娘に恋をし、反対に会いながらもなんとか結婚にこぎつけると、その喜びから1840年(シューマン歌の年と言われています)猛烈な数の歌曲を一気に書き上げました。
その人の人生そのものがロマン派と言える作曲家です。その歌曲の中でも特にロマンティックな音楽で知られているのがハイネの詩に作曲された歌曲集「詩人の恋」です。秋の夜長に、いかがでしょうか。今週はちょっと宣伝になってしまいました。
音楽と私(第16回)
前回モーツァルトとシューマンについての話題でしたので、ついでにもう一人僕の大好きな作曲家について書こうと思います。それはシューベルトです。
シューベルトは歌曲が有名ですが、知られているのはそのほんの一部、「野バラ」「魔王」などのわかりやすい曲のために小市民的な作曲家と思われがちです。歌曲以外では「未完成交響曲」などを除いてそれほど人気がありません。単調で長く、面白みがないと考えられてしまう場合が多いようです。
実はこの単調で、繰り返しが多く長い曲が、じっくり聴いていると良くなってくるのです。華やかなショパンの曲は確かに素敵ですが、作曲家の人生や、演奏者の音楽への思い入れなど、生身の人間の心がにじみ出てくるのがシューベルトのピアノ曲や室内楽です。
演奏を通じて、本当に伝えたいものは、演奏者の技術ではなく、やはり心ではないでしょうか。そこには音楽の聴き手の人間性までが問われてくるところがあります。マイクやスピーカーを使わないからこそ伝わる部分があると思います。やはりクラシック音楽は素晴しいですね。無理矢理のまとめでした。
私と音楽(第17回)
唐突ですが、歌はどうして人の心を打つのでしょうか。音楽の始まりは歌だと言われています。
まだ言葉もなかった頃、人間は感情の高ぶりを抑揚のついた声で表現するうちにメロディを歌うようになりました。また遠くの人に何かを伝えるためにも歌う事は必要でした。声を出す声帯の構造は正確な音程を作る働きをもともと持っています。
つまり歌を歌うというのは、すべての人に与えられた人間の特徴なのです。せっかくの機能なのに現代人は、感情を露骨に表に現す事を押さえたり、むやみに大きな声を出して歌う事を恥ずかしい事と教えられたりするうちに、この歌うという機能を、残念ながらどんどん退化させてしまっています。
モーツァルトの時代、最もテクニックを持った楽器は歌だったのです。人は感情が高ぶったときに思わず大きな声を出してしまいます。眠っていた歌う機能が呼び覚まされ、自然と声を響かせる状態が体の中でよみがえります。悲しみにつけ喜びにつけ、この状態で出された声にはその感情に伴った声の色を持っています。それを聴いた人は、声の色から、声を出した人の感情を聴き取り、同じ感情を疑似体験するのです。
表情のある歌声は、詩の内容やメロディの持つ情感を声の色や響きで的確に聴く人に伝える事ができます。どうしたら情感のある歌声を出せるのでしょうか?僕の発声の先生は、いつも野生に返る事が大事だと言っていました。単純な性格であっけらかんとした人は、しゃべり声も大きいし良い声で歌いますよね!
ここから2007年
私と音楽(第18回)
「のだめカンタービレ」って見ていましたか?今頃こんなことを言っているのはかなり遅れているとお思いでしょうが、実はつい最近になってこのドラマを全部見ました。
放送されている時は、タイトルに惑わされ見る気がしなかったのですが、特に音楽関係の知り合いより、はまっているという話を聞きました。その後たまたま通っている歯医者さんのロビーに単行本の漫画が置いてあったのを手にしてよりのファンとなってしまいました。
早速知り合いからDVDを借りて見たところ、実にすばらしいドラマでした。いろいろな場面での主人公のセリフが、音楽の本質を見事にとらえているのです。薄っぺらな笑いの中に、音楽に取り組んでいる人間にはなるほどと思える貴重な言葉が、数多くちりばめられているのに驚きました。もともとコミックのドラマ化なので少々くだらないギャグも多いし、作者が指揮者については知識が少ないのか、指揮者が楽員に出す指示があり得ないものだったりする点を除けば、内容的には「アマデウス」に匹敵する音楽を題材としたドラマではないかとすら思えます。
ドラマに登場する曲の選曲が本当にいいですね。全部僕の大好きな曲ばかりです。ドラマのテーマは、キッチリと楽譜通り弾くことを大切にしてきた優等生の指揮者志望の若者が、一見ハチャメチャでまったく評価されていないが、音楽の本質をとらえた自由で本当に人を感動させる演奏をするピアノ科の少女に出逢い、音楽家として成長してゆくというものです。まだ見ていない方にはオススメです。ちなみに全11回です。
私と音楽(第19回)
前回からの話に通じるのですが、音楽家は何を目指して日々練習して膨大な時間を費やしているのでしょう。
今の時代ただ正確に早いパッセージを演奏するならコンピューターに任せておけば良いのです。現実にポップスの世界のレコーディングでは音のサンプリングのみに実際の楽器をならして、あとはコンピューターで音を作ってしまうケースが増えているようです。細かいニュアンスまでコンピューターで作ることが出来て、一般の人には違いがわからないくらいまでに進歩しています。
歴史的な天才が作った曲をその通りに演奏するクラシックでは、すでにきら星の如く名演奏が録音として残っていて、誰でも気軽に手に入れることが出来ます。それでもその曲をさらに演奏する意味はあるのでしょうか。それにはなぜ人は音楽に感動するのかという原点の問いに戻る必要があります。どれだけ演奏者が演奏する曲について、真剣に取り組んだかが重要なのです。その気持ちが音楽に現れた時に聴衆は感動するのです。
ドラマ「のだめカンタービレ」では、シュトレーゼマンという指揮者が言っています。まさに、なぜ第九が感動を呼ぶのかの答えでもありますね。初めて第九を歌う方は諦めそうになることもあるかもしれませんが、がんばってとにかく練習に参加して下さい。
大事なのは周りのメンバーを信じて一緒に本番の日まで全力で取り組むことです。
私と音楽(第20回)2007.8.9第753号
以前書いた記憶がありますが、作曲家が曲を作る時に、美しいメロディを中心に曲を作るタイプと音楽の断片を組み合わせてレンガ造りの家のように曲を構築していくタイプに分かれます。
前者の代表は、ショパンやドヴォルザークがいます。また後者の代表は、ベートーヴェンやブラームスあたりでしょうか。もちろんベートーヴェンやブラームスも美しい旋律を残してはいますが、メロディ中心の作曲は得意ではなかったようです。ブラームスはドヴォルザークのメロディを生み出す才能をうらやんで、「やつのゴミ箱から拾ったメロディで交響曲がいくつも作れる」と言ったそうです。
有名な作曲家の中にもメロディを作るのが得意でない作曲家がいます。歌曲の王と言われるシューベルトでさえ実はそんなに美しいメロディは残していません。どうですか、シューベルトの歌曲で思い浮かぶメロディはありますか?代表作の「野ばら」や「魔王」もメロディらしいメロディはないのです。ただ「セレナーデ」と「アヴェ・マリア」はご存知のように名旋律で作られています。
それではわが日本はどうでしょう。たくさんの日本歌曲がありますが名旋律と言えるような曲は残念ながら僕は知りません。ところが最近クラシックの曲以外で、すばらしいメロディに出会いました。
時代を超えてその美しさや表現力を失わないメロディ。それは古賀政男のメロディです。いままでクラシックにとらわれていたために見過ごしていましたが、「影を慕いて」「悲しき酒」などは世界に通用するメロディではないでしょうか。
実は、9月の演奏会(於:岩宿資料館)でその「影を慕いて」をシューベルト風のピアノ伴奏で歌うことにしています。(ちょっと宣伝)
私と音楽(第21回)2007.8.16第754号
前回の文で、若い頃はクラシックの曲ばかりにしばられて本質的なすばらしい音楽に気がつかなかったと書きましたが、クラシック音楽とそれ以外の音楽の差は何でしょうか。その答えは簡単そうで結構難しいところがあります。
クラシックの音楽の一つの特徴として、その芸術的な価値をとことん追求するという姿勢があります。しかし演歌歌手なども、同じ曲の隅々まで一点の曖昧さもなく磨き上げ、その点では、まさに芸術といえるかもしれません。
逆に多くのクラシック歌手は、声に頼ってしまいそこまで完成度のないまま演奏会にかけてしまう場合があるのも事実です。また生の音のみで演奏するという点もクラシック音楽の特徴と言えます。
同じように生で演奏することの多いジャズ音楽との違いはどうでしょうか。ジャズとクラシックの大きな違いの一つは、ジャズは完全な譜面を書かない点です。大まかな中心のメロディと和音進行のみの打ち合わせで、だいたい決められた小節数だけアドリブで音楽をつないでゆきます。
この点について実は、クラシック音楽も昔はおおいにアドリブが楽しまれていたのです。モーツァルトは少年の頃父に連れられて各地の貴族の館で演奏会をしましたが、その時、集まった人の中からメロディを与えてもらい、そのメロディを使って即興演奏をしてみせましたし、20才でウィーンにやってきたベートーヴェンは、情熱的な即興演奏で聴衆を熱狂させたと伝えられています。もともとはクラシックの演奏者は即興演奏も得意だったのです。
合唱団のトップページ / 高崎第九のあゆみ / ベートーヴェンと第九 / 海外公演