第28回演奏会 2001年12月22日
下記内容は、財団法人群馬交響楽団から得た情報を元に高崎第九合唱団で加筆しています。絶対にコピーや引用はおやめください。指揮者 沼尻 竜典(Ryusuke Numajiri)
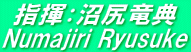
1964年東京生まれ。
桐朋学園大学において、指揮を小澤征爾、秋山和慶、尾高忠明、作曲を三善晃、ピアノを徳丸聡子、藤井一興の各氏に師事。
大学在学中から新日本フィルハーモニー交響楽団で小澤征爾氏のアシスタントとして活躍。
また同時期、NHK交響楽団および東京フィルハーモニー交響楽団で鍵盤楽器奏者として数多くの演奏会に出演。
1989年渡独、ベルリン国立芸術大学でハンス・マルティン・ラーベンシュタイン教授に師事。
1990年9月、第40回ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。
以後トュールーズ・キャピトル劇場管弦楽団、パリ室内管弦楽団、チューリンゲン・フィル、シュターツカペレ・ワイマール、アウグスブルク・フィル、ノーザン・シンフォニア(イギリス)、オーデンセ交響楽団(デンマーク)、ハイファ交響楽団(イスラエル)などを指揮した。
1998年ミラノ交響楽団ジュゼッペ・ヴェルディを指揮してエヴィアン音楽祭に出演するなど成功を収め、着実にヨーロッパでの実績を重ねつつある。
1998年10月にはロンドン交響楽団にデビュー、1999年1月に再客演を果たし、その際に演奏曲目の1つであるグヴァイドゥーリナの作品を、ロストロポーヴィチのソロと共にEMIにレコーディングした。
この他にも世界のトップ・アーティストとの共演も数多く、A・S・ムター、F・P・ツィンマーマン、Z・コチシュ、B・L・ゲルバー、J・P・コラール、S・カツァリス、M・ベロフ、K・ライスター等といった名が挙げられる。
国内では1991年「若い芽のコンサート」でNHK交響楽団を指揮してデビュー。
その後定期的に全国の主要オーケストラを指揮、好評を得ている。
1993年から1998年まで新星日本交響楽団の正指揮者を務めた。
作曲、ピアノ、指揮の総合的な豊かな才能を活かし、定期公演をはじめ、独自の企画に臨み、オーケストラの発展に寄与した。特に94年グレツキ「悲歌のシンフォニー」日本初演、95年ヨーロッパ・ツアーの成功、ワーグナー「ワルキューレ」第1幕、96年メシアン「トゥランガリラ交響曲」、97年マーラー「交響曲第6番」、シェーンベルク「期待」、98年ラヴェル「ダフニスとクロエ」、マーラー「復活」の成功は特筆される。
1995年、自らの呼びかけで結成されたトウキョウ・モーツァルト・プレーヤーズと共に、三鷹市芸術文化センターを拠点に活動を開始。
EXTONレーベルへの録音も行っている。
1999年4月より東京フィルハーモニー交響楽団の正指揮者を務めている。
オペラ指揮者としての活躍も期待されており、97年「後宮からの誘拐」でデビュー、その後も「フィガロの結婚」、98年「シンデレラ」「セヴィリアの理髪師」、99年も「ラ・ボエーム」「ヘンデルとグレーテル」を指揮。
また98年に開館したびわ湖オペラの青少年向けオペラの指揮も担当している。
現代音楽にも深い理解と造詣を持ち、数多くの日本初演を行った。
中でもリゲティ、ルトスワフスキ、ベリオ、デュティーユー等の作品の初演では、その緻密な解釈と的確な指揮が作曲者自身にも「完璧な解釈」と高く評価された。
また東京都交響楽団を指揮し、武満徹の作品集を3枚、DENONにレコーディングしている。
1999年4月より東京フィルハーモニー交響楽団正指揮者、2001年4月より名古屋フィルハーモニー交響楽団首席客演指揮者を務めている。
2001/02シーズンは東京フィル、札幌交響楽団、名古屋フィル等の定期公演を指揮するほか、ベルリン交響楽団、デュッセルドルフ・トーンハレ交響楽団へも客演予定。
1991年、第1回「出光音楽賞」受賞。
1995年、第64回日本音楽コンクール・ヴァイオリン部門でのバルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」の指揮に対し、コンクール委員会特別賞受賞。
1999年、第7回「渡邉暁雄音楽基金音楽賞」受賞。
2001年、第51回「芸術選奨文部科学大臣新人賞」をそれぞれ受賞。
高崎第九合唱団との共演は初めて。
ソプラノ 飯田 実千代(Michiyo Iida)
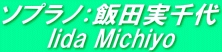
京都大学教育学部教育心理学科卒業。
声楽を故引田リエコ氏、マルタ・ランティエリ氏、スザンナ・ギオーネ氏に師事。その他イタリアとウィーンにおいて、スザンナ・リガッチ氏、イリス・コラデッティ氏、ジャンニ・ラィモンディ氏のマスタークラス修了。
1990年日本イタリア声楽コンコルソ金賞、日伊声楽コンコルソ第2位、飯塚新人音楽コンクール大賞、朝日ABCコンサート優秀賞、NHKFM新人オーディンョン合格。
「ヘンゼルとグレーテル」グレーテル役でオペラデビュー。
「椿姫」ヴィオレッタ、『リゴレット』ジルダ、「ランメルモールのルチア」ルチア、「愛の妙薬」アデイーナ、「セヴィリアの理髪師」ロジーナ、「こうもり」ロザリンデ、ヴォルフ・フェラーリ「スザンナの秘密」スザンナ、「ねじの回転」家庭教師、「ラ・ボエーム」ミミ、「夕鶴」つう等に出演。
「第九」や「メサイヤ」、「天地創造」など交響曲、宗教曲などのソリストを務め、日本だけでなくイタリア、ドイツ、オーストリアにおいてもコンサートやリサイタルなどに出演。幅広く活躍している。
二期会会員
高崎第九合唱団との共演は初めて。
メゾ・ソプラノ 高尾 佳余(Kayo Takao)
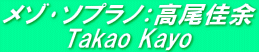
国立音楽大学、同大学大学院オペラコース修了。
田島好一、M.B.カゾーニ、L.ゴルラ、C.コンドレア、N.トゥトゥザムスの各氏に師事。
1996年大学院在学中に第32回日伊声楽コンコルソ第1位。
第4回多摩フレッシュコンクール声楽部門第1位入賞。
1997年よりリクルートスカラシップオペラ奨学生として2年間ミラノにて研鑽を積みながらコンサート活動を行う。
国立音楽大学大学院オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」ドラベッラでデビュー。
第65回読売新人演奏会、新宿文化会館推薦音楽会、サントリーホールデビューコンサート等に出演。
また、第12回国民文化祭、京都国際音楽フェスティバル、ニューヨークのカーネギーホールにおいてオペラ、宗教曲、コンサート等の活動を行う。
1999年にはチェコ共和国、プラハにて「マレーバプラハ国際音楽祭」に出演。
またチェコ各地でコンサートを行い、同年日本での「チェコ共和国芸術祭」でチェコ語による演奏会に出演。
2000年6月新国立劇場に「リゴレット」のマッダレーナでデビューし、2001年6月には「蝶々夫人」のスズキで好演する。10月には新国立劇場小劇場シリーズ「花言葉」に出演予定。
その他、2001年東京フィルハーモニー交響楽団のニューイヤーコンサート、新日フィルの第九など、各種コンサートに出演している。
現在、ドイツのデュッセルドルフに留学中。
藤原歌劇団団員。
高崎第九合唱団との共演は初めて。
テノール 中鉢 聡(Satoshi Tyubachi)
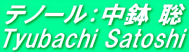
1966年生まれ。秋田県湯沢市出身。
東京芸術大学音楽部声楽科卒業。
日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第11期生修了。築地利三郎、鈴木寛一の両氏に師事の後、現在、南條年章氏に師事。
1992年ロッシーニ国際オペラ・コンコルソ入選。
平成5年度文化庁芸術家国内研修員。
オペラ歌手育成部在籍中の1990年、秋田県制作の郷土オペラ「ねぶり流し物語」の三郎でデビュー、続いてモーツァルト「バスティアンとバスティエンヌ」のバスティアンに出演し、修了公演では「オリー伯爵」のタイトルロールを歌った。
その後、「カルメル会修道女の対話」、東成学園オペラ「ミトリダーテ・エウパトーレ」、同オペラ「オリーヴォとパスクアーレ」(日本初演)、豊島区民オペラ「ボッカッチョ」等に出演。
1995年「椿姫」のガストンで藤原歌劇団にデビューを飾り、96年「東洋のイタリア女」(日本初演)のシーシンで好評を博す。その後イタリアに渡り、ミラノにてボッケリーニの「スタバト・マーテル」などのコンサートに出演。
1997年は藤原歌劇団文化庁青少年芸術劇場公演「愛の妙薬」のネモリーノを歌い、「椿姫」のガストンは1998年、99年の本公演や文化庁移動芸術祭公演で歌っている。
2001年7月「イル・カンピエッロ」に出演。
新国立劇場には開場記念公演「建・TAKERU」の両面少名でデビュー後、99年に「こうもり」のアルフレート、「マノン・レスコー」のエドモンドで好評を博し、2000年は「セヴィリアの理髪師」(藤原歌劇団共催)のフィオレッロ、「ドン・キショット」、「魔笛」に出演している。
また2001年3月にNOP公演の「耳なし芳一」、5月には東京室内歌劇場公演の「ラマンチャの男ドンキホーテ」で両タイトルロールに出演、絶賛を博す。
7月には藤原歌劇団「イル・カンピエッロ」で好演。
8月には文化庁体験劇場「愛の妙薬」に出演。
その他、「第九」やドニゼッティ「レクイエム」のソロ、各種コンサートで活躍し、NHK教育テレビ「愉快なコンサート」にもレギュラー出演した。
1993年と94年にリサイタルを開催。アジリタのテクニックを備えたリリコ・レッジェーロで美声、美貌のテノールとして今後の活躍が大変期待されている。
藤原歌劇団団員。
高崎第九合唱団との共演は初めて。
バリトン 大島 幾雄(Ikuo Oshima)
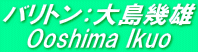
1974年桐朋学園大学卒業。
1978年オペラ研修所第1期生修了。
萩谷納、伊藤武雄の両氏に師事。
美声と豊かな音楽性は高く評価され、1979年第7回ジロー・オペラ賞を受賞。
同年11月より文化庁派遣芸術家在外研修員としてミラノに留学しさらなる研鑚を積んで翌1980年に帰国した。
オペラには1975年ラヴェル「スペインの時」ラミーロでデビュー。
1976年「タンホイザー」のビーテロルフで二期会オペラにデビュー。
早くからバリトンの逸材として注目を浴び、その後「フィガロの結婚」「ルチア」「蝶々夫人」「利口な女狐の物語」「ドン・カルロ」「ニュルンベルクのマイスタージンガー」「ドン・ジョヴァンニ」「ファルスタッフ」等の二期会オペラに次々と主演。
1985年には難役といわれるベルクの「ヴォツェック」タイトルロールで見事な歌唱を聴かせ、一躍その評価を高めた。
その後も「愛の妙薬」ベルコーレ、「ペレアスとメリザンド」ペレアス、「神々の黄昏」グンター、「ポッペアの戴冠」オットーネ、「ラインの黄金」ドンナー等の難解な役柄を次々とこなす一方、「こうもり」のファルケ等オペレッタや、邦人作品の初演にも意欲的に取り組み主演するというレパートリーの広さ、硬軟とりまぜた演唱力には抜きんでたものがある。
1994年7月至難な技巧を要する「トロヴァトーレ」のルーナ伯爵を見事に演じ、その的確な役作りと魅力的な仮想は高い評価を受けた。
また1994年10月には、文化庁芸術祭主催公演バーンスタイン「ミサ」において司祭役を熱演。
1997年2月には二期会公演「パリアッチ」でシルヴィオをつとめるなど、二期会を担うプリモ・バリトンとして注目を浴び、11月には新国立劇場開場記念公演「ローエングリン」にテルムラント役を演唱し、演出のヴォルフガング・ワーグナーより最大級の賛辞を送られた。
また1998年9月新国立劇場・二期会共催公演「アラベッラ」マンドリカ役でも端正でありながら表現豊かな歌唱を絶賛された。
以後J・フルネ指揮・都響「ペレアスとメリザンド」ゴロー、びわ湖ホール「ドン・カルロ」ロドリーゴ、東京室内歌劇場「狂ってゆくレンツ」、サントリーホール「ルル」(演奏会形式)と多様な役を歌いこなしてレパートリーを広げている。
2002年7月二期会公演「ニュルンベルクのマイスタージンガー」にベックメッサーで出演予定。
またコンサート歌手としても多くの実績を持ち、ベートーヴェン「第九交響曲」始めとしてバッハ「ロ短調ミサ」「マタイ受難曲」、ヘンデル「メサイヤ」、ブラームス「ドイツ・レクイエム」、フォーレ「レクイエム」といった宗教曲から、マーラー「亡き子を偲ぶ歌」「交響曲第八」、オルフ「カルミナ・ブラーナ」まで幅広い作品のソリストとして国内のあらゆるオーケストラ、内外のあらゆる著名な指揮者と共演しており、その実力を多いに認められている。
二期会会員。
高崎第九合唱団との初共演は、1977年の第4回演奏会である。
その後の共演は1983年のNHK交響楽団と共演した第10回演奏会、1991年の第18回、1992年の第19回であり、今回で5回目となる。
