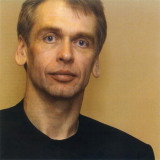指揮:ギンタラス リンケヴィチュス
a conductor:![]()
ギンタラス リンケヴィチュス氏は1988年にリトアニアン・ステイト・シンフォニー・オーケストラを創立。そして1996年から2003年まで同オーケストラで、2003年からはスウェーデン マルモ オペラにて芸術監督、チーフコンダクターを務めている。また同氏はモスクワのボリショイ劇場でロミオとジュリエット、スペードのクウィーン、ラ・ボエーム等の公演の指揮をしている。
同氏はヴィリニュスのM. K. Ciurlionis School of ArtstoとSt.Petersburg Conservatoireで学び、1983年から1986年まで、Moscow ConservatoireでYuri Simonovについて修士課程を学んだ。同氏は幸運にも指揮者のコンテストに3回出場し、1983年には旧ソビエト、モスクワの「第5回 モスクワ指揮者協会コンテスト」の優勝者になった。1985年には西ベルリンで行われたカラヤン基金コンテストでも優勝、1986年にはJanos Ferencsik記念ブタペストコンテストでも入賞した。
同氏はリトアニアン・ステイト・シンフォニー・オーケストラを率いて、フランス、オランダ、イタリア、ルクセンブルグ、ドイツ、スペイン、イギリス、オーストリアを廻り、一流の音楽祭に出場した。スウェーデンでは1998年、マルモオペラ劇場でのビゼーのカルメンでデビューを飾った。1999年にはノルウェーのオスロ劇場から招待を受けた。その他、ラトビア国立オペラ劇場、リトアニア国立オペラバレー劇場など、一流の劇場で数々の公演を成功させた。
1994年と1996年にはオーケストラの業績に対し、リトアニア国家栄誉賞、1997年にはラトビアから国際音楽賞、1998年にはノルウェー、2004年にはポルトガルで賞を授けられている。また同氏はリトアニア音楽アカデミーの教授でもある。
スィグテ・ストニーテはリトアニア音楽アカデミーを卒業。
1985年よりリトアニア国立オペラバレー劇場で、ソプラノのリーダー的存在として活動を続けている。
1984年、リーガで行われた国際声楽コンクールで入賞。1991年にはアメリカのメリーランド州で開催された、マリアンアンダーソン ボーカリコンテストで第2位に入賞している。(1位は該当者なし)1996年リトアニア芸術協会は彼女にクリストファー賞を贈り、1999年にはリトアニア国内のベストシンガーと評され、2004年にはリトアニア国際賞を受賞した。
彼女はリトアニア国内の作曲家達によるオペラでも活躍している。豊富な室内音楽の作品をレパートリーに持ち、バッハからブリテンまで30以上ものソプラノパートを担当している。そしてリトアニアン ステイト シンフォニー オーケストラのツアーにも参加している。
オペラでの役名はVioleta(La Traviata),Lady Macbeth(Macbeth),Abigaile(Nabucco),Leonora(ⅡTrovatore),Aida(Aida),Margarita(Faust),Tatiana(EugeneOnegin),Cerubino(LeNozzediFigaro),Elisabeth(Tannhauser),Marzellina(Fidelio),Agathe(DerFreischutz),Tosca(Tosca),Senta(Der fliegende Hollander)
メゾ・ソプラノ:イネサ リナブルギーテ
a mezzo-soprano:![]()
イネサ・リナブルギーテは1966年、リトアニアのクライペダで生まれた。
一番先に学んだ音楽はヴァイオリンであった。その後、リトアニア音楽アカデミーで声楽を学んだ。
1992年、優勝な成積で卒業し、リトアニア国立オペラバレー劇場から誘いを受けた。彼女は短期間で非常に難しいパートをいくつもこなせるようになっていった。最近の出演作品はアイーダのアムネリス、カルメンのカルメンとメルセデス、サロメのエロディアーダ他。コンサートレパートリーには交響曲の作品と同様に、室内楽の作品もある。彼女は多くの国際コンクールにも参加し、近年は特に良い成績を収めている。
アルギルダス・ヤヌタスの声楽はミンスクのM.Glinka音楽学院、リトアニア音楽アカデミーで学んだ。
リトアニア国立オペラバレー劇場で活動を開始し、最近はリトアニア国内に止まらず、ラトビア、ドイツ、フランス、イギリス、アルゼンチン等でも活躍している。オペラの役柄を通して非常に沢山のレパートリーを持てるようにもなった、同氏はしばしばリトアニアン ステイト シンフォニーオーケストラやリトアニアン チャンバー オーケストラと共に活動している。また、ラトビア国立交響楽団、ロンドンロイヤルハーモニー、スコットランド ロイヤルオーケストラやサンクトペテルブルグ等のオーケストラとも共演し国際的な活躍をしている。
リュダス・ノルワイシァスはリトアニア国立オペラバレー劇場で1984年からソリストとして活動を続けている。1996年~2000年まで、いくつかのドイツの劇場と契約をしてきた。最近の役柄は、Professor(The Bear),Filippo Ⅱ and Grand Inquisitor(Don Carlos),Cesare Angelotti(Tosca),ⅡGrand Sacerdote(Nabucco),Tom(Un ballo in maschera),Leporello(Don Giovanni),Zuniga(Carmen)etc.
リトアニアン・ステイト・シンフォニー・オーケストラの創設者、芸術監督、主席指揮者はギンタラス・リンケヴィチュス氏である。
同オーケストラは1988年に創設され、1989年1月30日に第1回目の演奏会を開いた。1999年に創立10周年を記念して最も新しく大きな、ヴィリニュス・コングレスホール(約1000席)で演奏会を開き聴衆を大いに感動させた。
創立から16年の間、900回を超える演奏活動を国内は勿論のこと、フランス、スペイン、イタリア、ドイツ、オランダ、イギリス、オーストリア、ギリシャ、台湾などでも行い、行く先々で観衆の歓声や評論家の暖かい評価に応えて演奏した。
同オーケストラは毎年、国際的な交響楽団の名作や声楽を加えた大規模な交響作品、コンチェルト、様々な国内外の作曲家等、新しい作品をレパートリーに加え聴衆を魅了してきた。リトアニアで行われた演奏会も演出、有名なゲストソリスト、考え抜いた選曲など全ての演奏会を大成功で終えている。同オーケストラは今までトスカ、トウーランドット、サロメ、トスカ、さ迷えるオランダ人など、9回のオペラも上演している。又、何枚ものCDも制作している。
合唱:高崎第九合唱団
a chorus:![]() (Japan)
(Japan)
1974年ベートーヴェンの第九交響曲を演奏するために創立。以来、年末に群馬交響楽団と共に「第九」を群馬音楽センターの舞台で歌い続けている。
1989年当時西ドイツのハイデルベルク市の聖霊教会において、日本の第九コーラス初となる海外公演を行い全国的な注目を浴びる。1995年高崎市の姉妹都市であるチェコのプルゼニ市では、プルゼニ市制700周年記念事業として第九を公演した。1998年ドイツのニュルンベルク市では、グスタフ・アドルフ教会において第九を公演し、通路や階段にまであふれた大観衆の喝采を浴びた。2002年ポーランドのザブジェ市聖アン教会での第九公演は、文化庁「地域文化国際交流事業」をはじめとする両国の各種国際交流事業に指定され、首都ワルシャワでの交歓演奏会、世界最深の岩塩ホールやアウシュヴィッツ収容所跡地など随所において歌による国際文化交流・人類平和を訴え続けた。
杉原千畝「6000人の命のビザ」で有名になったバルト三国のリトアニア、その首都ヴィリニュスにおいて2006年6月、リトアニア国立オーケストラとの『世界平和のための第九コンサート』を開催する。あわせてバルト三国・デンマーク・フィンランドを周遊し音楽による文化交流を目指す。コーラス団員、随行希望者を若干名追加募集している。
自ら企画・運営・主催・契約・販売・法手続きも行っている市民コーラスとしての活動は高く評価されている。団員は年齢も職業も様々であるが、多くの群馬県民のほか、東京・埼玉・栃木・新潟からも練習に参加している。ベートーヴェンの音楽を愛し、「第九」の人類愛の精神を歌い、音楽による平和と国際文化交流を目指すことを共通の信念として活動を続けている。