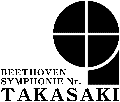この分割によりプロイセン領となった地域を今でもシレジア地方と呼び、ドイツ北部・チェコ・ポーランド西部にかけて独特の文化・民族・言語を継承している。ポーランド国内のこの地方はドイツに親しくドイツ訛のポーランド語が残り、民族衣装や踊りなどにも共通点が多い。この地方の最東端がカトヴィッツェであり、現在もシレジア地方会議の議場地として機能している。このカトヴィッツェからわずか50km東にあるポーランド王国の首都だったクラクフは、三国分割の際オーストリアに編入され、第一次世界大戦終了まで異なる歴史を歩むことになる。
今回の演奏の地は、そのカトヴィッツェの西隣ザブジェである。ザブジェは人口約20万人の市で、ポーランド国内ではよく知られている都市である。観光地ではないのでガイドブック等には載っていない。というのもこの市の歴史は浅く、1922年に5つの町村が合併して市となったためで城郭も中央広場もない。第二次大戦及び、大戦後の冷戦によって都市計画は遅れてしまい、民主化した現在本格的な再開発が行なわれようとしている。ザブジェ市の20世紀は石炭・鉄鋼産業が盛んで多くの労働者が集まり、鉄道・交通の要衝として栄えた。しかしこの石炭産業を支えていたのは、第二次大戦でこの国をナチスから解放し同胞として迎え入れたソビエトである。冷戦の終結、民主化によって石炭は必要とされなくなり、産業の転機を迎えている。近年日本のトヨタ自動車を始めとする機械産業、貿易商社、電子工業、建築業等が進出し、ポーランド国内の生活様式の変化・向上に貢献している。
ザブジェ市は文化面で特に優れている。多くの労働者を抱えるため市内の至る所に劇場やコンサートホールが点在する。20万人規模の都市では維持すら難しいというのにプロ・オーケストラ「ザブジェ・フィルハーモニック・オーケストラ」が活躍し、国内外での演奏を行なっている。このことは、私たち高崎第九合唱団が拠点としている高崎市(人口24万人)がプロの「群馬交響楽団」を持っていることとよく似ている。群馬交響楽団は日本で2番目の歴史というだけでなく、チェコの「プラハの春音楽祭」に招致された経歴も持ち、私たち高崎第九合唱団創設時からのパートナーである。
今回の指揮者フジャノフスキー氏はザブジェフィルの指揮だけでなく、客演として日本での公演経歴を持つ大の親日家である。今回の演奏に関してもフジャノフスキー氏自らザブジェフィルを率いて、名乗り出たことには敬意を表したい。
またポーランドの国民に親日家が多いという噂どおり、プロである指揮者・オーケストラ・ソリストという公演費用のすべてをザブジェ市が負担する旨の申し出があった。演奏会場は、劇場やコンサートホールではなく、市民の精神的な拠り所である市内最大の聖アン・ローマカトリック教会が、タルノフスキー司祭の絶大なる協力の下提供されることとなった。
第4回の演奏地を決定するにあたって、ドイツのボン(ベートーヴェン生誕地)など中欧・東欧から数都市の名乗りを得ていたが、これら背景とさまざまな諸条件を月1回の運営委員会で議論し、今回の結論を得たものである。もちろんポーランドが第二次大戦最大の被災国(独ポ不可侵条約破棄による大戦開始、国内600万人の犠牲者)であること、日本がドイツと同盟を結んでいたことは事実であり、熟慮を要したことに偽りはない。
この演奏会及び演奏旅行に関し、基本的事項・重要事項は当団運営委員会が討議・決定した。この内容を旅行業㈲国際文化交流センター(ICEC)が具体的に練り上げて、ポーランド側と交渉した。ICECは夫婦が主体となり運営する会社だが、その人脈と経歴は大手旅行会社をはるかに凌いでいた。日本各地の文化団体の国際交流事業、世界各地の文化団体の招致事業などに特化し、現地での旅行手配・演奏会・精神的な面まで実に細かく迅速にサポートしていただいた。公演企画の充実度、満足度の団員の評価は格段に高かった。
ポーランド側の手配窓口は、「センター・フォー・ポーランド・ジャパン・カルチャー」社の代表ミロスワフ・ブワシチャック氏(ミレック氏)である。ミレック氏は、ICECの夫婦と個人的な知り合いであるだけではなく、ワルシャワ市立タルノフスキェ・グリ文化センター館長であり、1990年から1994年まで、在日ポーランド大使館の文化担当官である故、非常に迅速かつ有効な手配を行なってくれた。ICECもミレック氏も当団の旅行に同行し一体となって行動したことも、99名の団員のトラブル回避に役立ち精神的苦痛を生まなかった要因であろう。
また、この度の文化庁平成14年度「地域文化国際交流事業」派遣の知らせは、大きな後押しとなった。一昨年からのテロ事件や戦争報道により企画見直しも心配されたが、文化庁の決定と各自治体の後援表明は、市民の心にある平和への願いに火を点す結果となった。第二次大戦後の復興に全力を傾けていた時期、産声を上げたばかりの市民オーケストラをプロ・オーケストラにまで育て上げた高崎市民の音楽文化を再現するような盛り上がりが見受けられた。また当然のことながらその知らせは、在ポーランド日本大使館の「ジャパン・ウィーク」行事と相まって、ポーランド国内を駆け巡りザブジェ市民にも伝わっていたことを付記する。「100万の人々よ、抱きあえ。この接吻を受けよ。」ベートーヴェンの愛がこめられた人類最高傑作の交響曲を片手に、平和のために異国の人々と今できる最善の方法で国際文化交流ができたものと確信している。この活動に終わらず、これからも私たちは平和の願いを歌い続けるが、もっと多くの人々に波及しもっと多くの人々が国際文化交流による平和を勝ち取れるよう切に願ってやまない。
ここに人類の歴史と文化の一部を実際に体験する機会、国際文化交流の機会を与えてくださった文化庁、群馬県、群馬県教育委員会、高崎市、高崎市教育委員会、群馬県教育文化事業団、在ポーランド日本大使館、この企画に参加・賛同してくださった多くの方々にすべての団員を代表し感謝の意を申し上げたい。
高崎第九合唱団 団長 渡辺義之
問合せ先
|