こんなにベタぼめされちゃっていいのかしら? でもうれしい
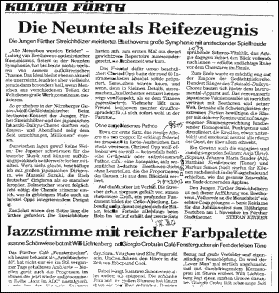
第九演奏会大盛況
フュルト市・シュトライヒホルツァーオーケストラ、ベートーヴェンの偉大な交響曲を喜びにあふれ熱演
ベートーヴェンの第九交響曲に示された、楽天的なヒューマニズムは、現代においても、その魅力を失っていなかった。その思想は今も輝きを失ってはいない、ましてや今回の演奏会のように 異なった国からやって来た人達との共演となればさらに明るい光を放つ。
演奏会はニュルンベルクのグスタフ・アドルフ 教会で開かれた。ベートーヴェンの曲が、シュトライヒホルツァーオーケストラと日本から来た、高崎第9合唱団により、昼と夜の時差のある国同士の共演によりSeid umschlungen, Millionen(抱き合え百万の人々よ)と、行われた。
オーケストラと合唱団の両者にはもはや国の違いによる隔たりはなかった。日本からの合唱団はドイツの音楽を良く理解し実際の演奏では自然に共演した。すばらしい日本の指揮者である鈴木雅明氏が、他のヨーロッパの指揮者同様にドイツ人演奏家のバッハを指揮するように、通訳はいらないのである。今回もクリステル・オップは全体を良くまとめていた。
まずオーケストラは、3つの楽章を練習しなければならなかった。今回のような大きな演目に挑戦するのは初めての彼等には練習期間はあまりなかった。注目すべき指導者は、60もの演奏者を、個別に指導した。 あまりに大きな曲の前に楽員達が後込みしないように、細かいところまで指導してベートーヴェンの巨大な作品に勇敢に立ち向かわせた。
誇張した情熱に偏らない均整のとれた演奏
第1楽章、アレグロ マ ノン トロッポ、静かな始まり、そして突然の噴火のようなフォルテ。クリステル・オップは、彼女の目指す音楽をしっかりと持っていた。それは、見せかけのおおげさな情熱ではなく、本質的に思慮深いベートーヴェンの視点に立った均整のとれた音楽であった。
丁寧に演奏に磨きをかけてきた楽員達は自信を持って演奏していた。基本のしっかりしているチェロパートに、生き生きと表情のある管楽器などによって第2楽章は飛び散るようなエネルギーを感じさせた。それに対比して、アダージョでは、心の内側を覗くような敬虔な静かな音楽が、それに続く激しい合唱の前に示された。
最後の楽章では、100人の高崎第9合唱団による合唱が、オーケストラの下、教会一杯に響きわたった。この評判の高い日本の合唱団はベートーヴェンの音楽とその世界を実によく理解していた。各合唱団員は非常に難しいパートを正確なテクニックと基礎的に統一された各パートの響きにより克服していた。リズムや発音は正確で、音の入りはよくトレーニングされていた。
ソロを歌ったメンバー、アニア・ウルリッヒ(ソプラノ)、ヨハンナ・マリア・サンダー(アルト)、マティアス・クライセルマイヤー(テノール)、マルクス・シモン(バス)も全力を出しきり、他の出演者同様、嵐のような拍手を受けた。
フュルト市・シュトライヒホルツァー・オーケストラは、このベートーヴェンの演奏会において大成功を収め、11月1日に15周年記念祭をむかえるフュルト市立劇場への最高のエールとなった



